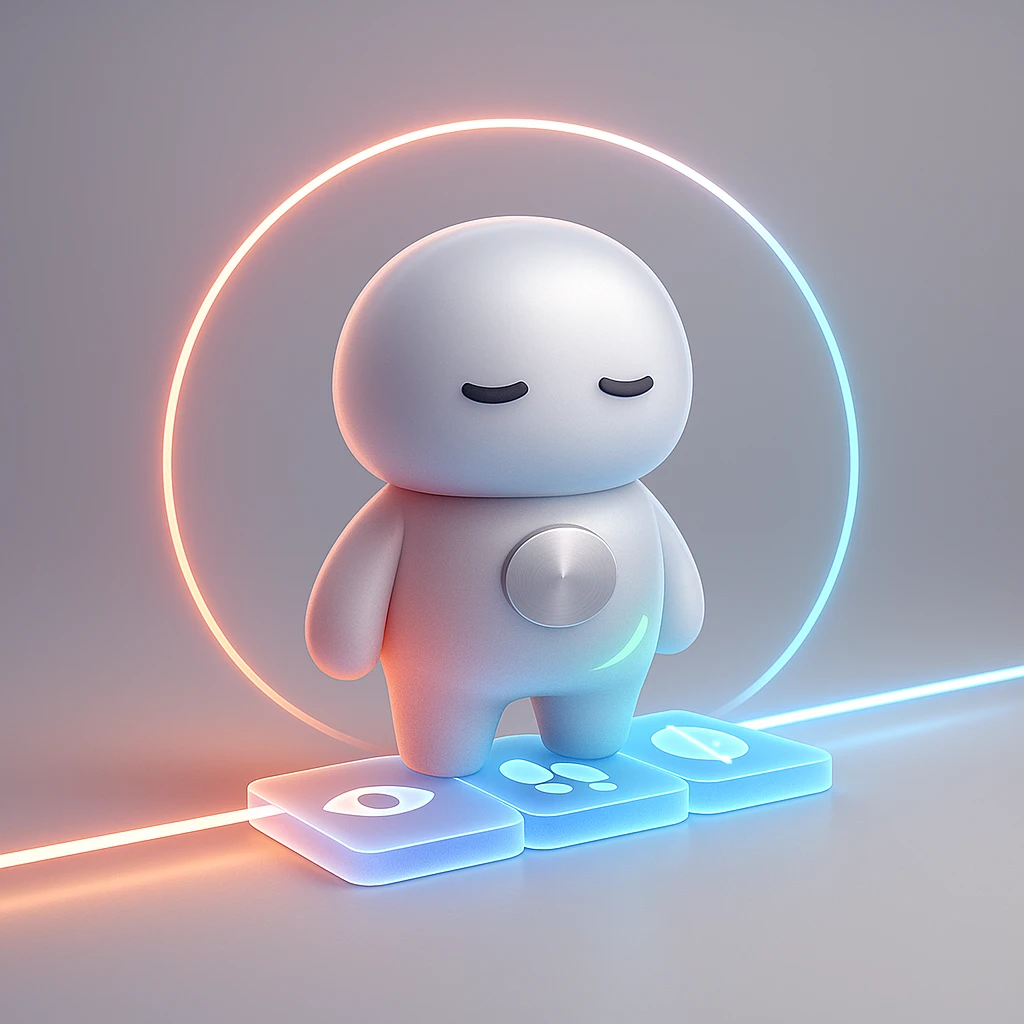仕事中に少しだけ休む。たったそれだけのことが、どれほど効果を持つのか。最近の研究は、10分以下の短い休憩「マイクロブレイク」と呼ばれるものが、疲労を減らし、モチベーションを取り戻すことを示しています。
ただし、すべての休み方が同じように効くわけではありません。何を改善したいのか、いつ休むのか、その間に何をするのか。この3つの組み合わせが、効果を左右します。
この記事では、発表された研究を中心に、マイクロブレイクの最新知見を整理しました。正解な秒数を探すのではなく、目的に応じた休憩の設計方法を、根拠とともにお伝えします。
マイクロブレイクとは何か

マイクロブレイクは作業の途中に入れる10分以下の短い休憩のことです。
実務でよく使われる60秒から180秒の休憩時間でも、疲労感や集中力に変化が起きることが確認されています。
脳には、一度に処理できる情報量に限りがあります。作業を続けていると、この処理能力が徐々に消耗します。短い休憩は、この消耗した脳リソースを回復させる機会になります。
何がわかっていて、何がまだ不確かなのか
22の研究と2,335人のデータをまとめた分析によると、マイクロブレイクはモチベーションを高め、疲労を減らすことが示されました。効果の大きさは小さめから中くらいで、年齢や職種、作業内容の違いに関わらず、ほぼ一貫して効果が現れていました。
一方で、作業成果への影響は、状況によって異なりました。単純な作業や創造的な課題では効果が出やすく、休憩が長いほど成果が上がる傾向もありました。ただし、難しい課題では、10分以下の休憩では回復が足りない可能性があります。つまり、「何秒休めば必ず成果が上がる」という一律の答えは、まだありません。
最近では、いくつかの新しい知見が加わりました。
大学の講義で、10分ごとに90秒のマイクロブレイクを入れた実験では、小テストの正答率が時間とともに下がりにくくなりました。休憩を入れなかった場合と比べて、中盤以降の成績の落ち込みが明らかに小さかったのです。
また、日常生活の中で休憩を促す研究も行われました。30分連続で座った後に、3分間歩くように促すと、気分やエネルギーの感覚が短期的に改善しました。この研究では、ウェアラブル機器で座っている時間を検知し、ランダムに休憩を勧める仕組みを使いました。日常に近い状況で、因果関係を確かめた点が新しいところです。
目的別に休憩を設計する

何を改善したいかによって、マイクロブレイクの取り方を変える必要があります。ここでは、目的ごとに推奨される方法と、その根拠、注意点を整理します。
モチベーションと疲労を整える
仕事の終わりに「疲れた」を減らし、モチベーション(研究用語では活力)を保ちたいなら、自分のサインに合わせて短い休止を入れるのが有効です。
サインの例:同じ箇所を何度も読み返してしまう/視線が画面から逸れる――といった小さな変化に気づいたら、数分のマイクロブレイクで区切る。それだけで十分です。
(研究上の定義では10分未満の短い休憩で、実際には3–5分や9–10分が多く報告されています。1–3分でも実務上は使いやすい時間幅です)
先ほど触れた分析でも、この効果が示されています。マイクロブレイクを多く取った日ほど、終業時の疲労は低く、活力は高いという関連がみられました。
ただし、休憩中に「何をするか」も回復度合いに影響します。
仕事とは関係ない休憩中の活動(散歩・ストレッチ・雑談・自然要素)は、その日の一時的な回復に結びつきやすい傾向があります。
仕事や作業と関連する休憩中の活動(次のタスクの整理・振り返り・同僚への支援など)は、瞬間的には負荷を上げる場合もありますが、繰り返すことで個人の成長・同僚や上司とのコミュニケーションによる社会的な関係性向上など、長期的なメリットにつながる可能性があります。
組み合わせもポイントで、たとえば体を動かすマイクロブレイク+軽い業務整理の併用は、活力の高さと関連していた報告があります。
学習で成果を上げる
講義や研修、学習など、長時間集中力を保ちたい場合、10分ごとに90秒の休憩を入れる方法が実証されています。
この方法は、イギリスの大学で、心理学の授業で試されました。253名の大学生と、全員同じ講師によって90分のセミナー形式授業を10週間にわたり受講し、一般的な45分経過で10分の休憩を1回だけ実施。マイクロブレイクとして10分ごとに90秒の短い休憩を入れるというグループに分け、90分の講義の最後に全12問の小テストを出したところ、マイクロブレイクを入れたグループは、入れなかったグループに比べて、小テストの成績が下がりにくかったのです。frontiersin
休憩の内容は、軽い伸張、水を飲む、目を閉じる、短い対話などです。難しいことをする必要はありません。
別の研究では、40秒間、窓の外の緑を見るだけでも、注意の持続が改善することが示されています。
ただし、高度に難しい課題では、もう少し長い休憩が必要になる可能性があります。課題の性質と休憩の長さの関係は、まだ完全には解明されていません。
気分とエネルギー感を即座に高める
今すぐ気分を上げたい、エネルギーを感じたいという場合、30分座り続けた後に3分間歩くことが効果的です。
2024年の研究では、日常生活の中でこの方法を試しました。参加者は、座っている時間が30分に達すると、ランダムに「歩いてください」という通知を受け取りました。通知を受けて歩いた後、気分の良さやエネルギーの感覚が上がったのです。
ここで重要なのは、ただ立つだけでなく、歩くことです。研究では、椅子から立つだけの場合よりも、歩行のような軽い有酸素運動の方が効果が高いことが示唆されています。
また、長さよりも、頻度と強度が鍵になるという指摘もあります。180秒を一度に取るよりも、60秒を3回に分けて、そのたびに少し動く方が、気分やエネルギーには効きやすいかもしれません。
なお、この研究では作業記憶のような認知機能には明確な差が出ませんでした。これは、参加者の能力が元々高く、測定の上限に達してしまった可能性があります。
目の疲れを和らげる
画面を長時間見続けると、目が疲れます。この疲労を減らすには、「20‑20‑20ルール」が役立ちます。
これは、20分ごとに20秒間、約6メートル先を見るという方法です。併せて、意識的にまばたきをすることも推奨されています。
2022年から2023年にかけて、このルールが目の疲れの自覚症状を減らすことを示す臨床研究が発表されました。ただし、涙の量や瞬きの質といった客観的な指標の改善は、短期間では限定的でした。症状の緩和という点では、実用性が高いと言えます。
加えて、イギリスの労働安全衛生庁(HSE)は、2025年に更新したガイダンスの中で、画面作業を行う人に対して、1時間あたり5分から10分のオフスクリーン時間を取ることを推奨しています。短い休憩を高い頻度で入れることが原則です。
首や肩、腕の負担を減らす
データ入力のようなキーボード作業を長時間続けると、首、肩、腕に負担がかかります。
2000年代初頭に、アメリカ国立労働安全衛生研究所(NIOSH)が行った現場研究は、追加のマイクロブレイクが、不快感や目の疲労を減らし、しかも生産性の低下はないことを示しました。
具体的には、1分から2分の能動的な休憩を、1時間に複数回入れる方法です。立ち上がり、肩甲骨を動かし、股関節を伸ばす。これだけで、筋骨格の負担を軽減できます。
手作業を伴う仕事では、10分ごとに1分の小休止と伸張運動を組み合わせることで、疲労を抑えつつ生産性を保てるとされています。
重要なのは、休憩を実際に取ること、つまり遵守率です。制度があっても使われなければ意味がありません。
休憩中に何をするかで、回復の質が変わる

休憩そのものに加えて、休憩中に何をするかによって回復の質は大きく異なります。例えば、Berigan & Pielage (2013) の研究では、自然風景を眺める休憩はテレビ番組視聴より注意回復傾向が強いと示唆されました。
また、7 分間の呼吸法実践は、ストレス感覚の有意な軽減と感情の安定化をもたらしたことが報告されています。
このように、休憩中の「刺激・行動内容」が、回復の質を左右する可能性が高いのです。
実際に使えるマイクロブレイクテクニック
ここでは、目的別に具体的な休憩の手順を示します。いつ、何を、どれくらいの時間行うかを明確にしました。
テクニック1:目のための休憩
20分ごとに20秒間、約6メートル先を見ます。その間、意識的にまばたきをします。その後、画面に戻ります。
テクニック2:姿勢のための休憩
立ち上がります。肩甲骨を寄せたり広げたりし、股関節を伸ばします。30秒から60秒かけて行い、座り直します。
テクニック3:呼吸のための休憩
4秒かけて息を吸い、1秒止め、6秒かけて吐きます。これを3回繰り返します。30秒から45秒ほどです。
テクニック4:自然を見る休憩
窓の外を見るか、自然の映像や壁紙を見ます。40秒から90秒ほど続けます。
テクニックE:歩く休憩
30分座り続けたら、3分間歩きます。気分やエネルギーを即座に高めたい場合に使います。血糖値を下げたい場合は、30分ごとに5分間歩きます。
休憩から作業に戻るときは、次に何をするかを一文で決めてから戻ると、スムーズです。注意を再び活性化させる助けになります。
いつ休憩を入れるか
休憩をいつ入れるかには、二つの考え方があります。あらかじめ決めておく方法と、状況に応じて判断する方法です。
会議や講義のように、時間の枠が決まっている場合は、最初から休憩を組み込んでおくとよいでしょう。90秒の休憩を10分ごとに入れる設計です。
一方、個人の作業では、適度に休憩を挟む方法が有効です。たとえば、30分連続で座ったら通知を出し、3分歩くことを既定の選択肢にします。ただし、それより前に集中が途切れたと感じたら、前倒しで休憩を取ることも許します。
もちろん30分に一度3分も歩くのが難しい場合などは、1-2分の徒歩などに調整しつつ、自分が休憩できたと感じられる時間と頻度で適度に調整するのがいいと思います。
よくある誤解
最後に、マイクロブレイクについてよくある誤解を整理します。
「短ければ短いほど良い」わけではありません。 難しい課題に取り組んでいる時には、もう少し長い休憩が必要な場合があります。作業や課題の性質と休憩の長さは、少し意識して対応するとよいです。
「立つだけで十分」ではありません。 気分やエネルギーを高めたいなら、徒歩のような軽い活動の方が効果的です。
「SNSで息抜き=回復」ではありません。 SNSは心理的に仕事から離れる感覚は得られますが、回復の質は疑問があります。適度に自然を見る方が、回復の質は高い傾向があります。
「睡眠を悪化させる」心配は不要です。 座る時間を分断して軽い活動を入れても、睡眠の構造には悪影響がないことが確認されています。
よくある質問
Q. マイクロブレイクって何分がベスト?“正解の秒”はありますか?
A. 一律の正解はありません。研究上は「10分以下の短休止」をマイクロブレイクと定義し、活力維持(モチベーション)・疲労感減少は一貫して有意ですが、成果への影響はタスクと休憩の長さ・内容で変動します。実務では“サインが出たら”60–180秒の小休憩、代謝や気分転換を狙うなら3–5分の歩行など目的別に使い分けを。40秒の自然の画像や映像に触れるだけでもマイクロブレイクによる効果が確認されています。
Q. 「10分ごとに90秒」みたいな休憩って、本当に学習や集中に効きますか?
A. 大学の実授業で10分ごとに約90秒のマイクロブレイクを入れた群は、通常の休憩グループより小テスト成績の失速が小さく、一貫性が高いという結果が示されています。一度自分で体験してみてどのような効果が現れるか確認してみるのがベストです。
Q. 休憩でSNSをサッと見るのはアリ?
A. 休憩しているな感覚は得られますが、疲労の回復は不完全になりがちで、自然を見るようなマイクロブレイクのほうが総合的に有利という実験結果があります。迷ったら“自然に触れる”をデフォルトに。
Q. 目の疲れには“20‑20‑20ルール”で十分?エビデンスは?
A. 20分ごとに20秒・約6m先を見る20‑20‑20は、自覚症状(デジタル眼精疲労・ドライアイ)の軽減を示した試験があります。一方で根拠は限定的とするレビューもあるため、過信するのはやめておくのが無難です。
Q. 短い休憩を増やすと、生産性は下がりませんか?
A. “下がらない”あるいは“むしろ維持・改善”とする研究が複数あります。
まとめ
マイクロブレイクは、モチベーションを高め、疲労を減らす効果が一貫して認められています。一方、作業の成績への影響は、課題の性質、休憩の長さ、休憩中に何をするかによって変わります。
自然を見る、歩く、目を休める、姿勢を変える、呼吸を整える。こうした活動を短時間で回すこと、そして休憩を入れる兆候に敏感になることが、実務での鍵です。
組織では、短く頻回に休むという原則を、就業の文化に組み込むことが推奨されます。効果は、主観的な感覚と客観的な指標の両方で検証できます。
こうしたマイクロブレイクの考え方に沿い、集中を保ちながら作業時間に応じて休憩時間を自動で計算するフロータイムテクニックを実践できるアプリを誰でも無料で使えるようにしています。トップページから試してみてください。
参考情報
- Albulescu P, et al. (2022). "Give me a break!" A systematic review and meta-analysis on the efficacy of micro-breaks for increasing well-being and performance. PLOS ONE
- Albulescu P, et al. (2025). Short Breaks During the Workday and Employee-Related Outcomes: A Multilevel Daily Diary Study. Psychological Reports
- Sustaining student concentration: the effectiveness of micro-breaks in university lectures (2025). Frontiers in Psychology
- Causal effects of sedentary breaks on affective and cognitive parameters in daily life: a within-person encouragement design (2024). npj Mental Health Research
- Dose-Response Analysis of a Randomized Crossover Trial: Breaking Up Sitting Time with Physical Activity (2023). Medicine & Science in Sports & Exercise
- The effects of breaks on digital eye strain, dry eye and binocular vision (2022/2023). Contact Lens and Anterior Eye
- UK Health and Safety Executive (HSE). Working safely with display screen equipment – Work routine (2025)
- NIOSH. Strategic Rest Breaks Reduce VDT Discomforts Without Impairing Productivity (2000)
- The impact of breaking up prolonged sitting with physical activity on sleep during simulated night and day shift work (2025). Scientific Reports
- 40-second green roof views sustain attention: The role of micro-breaks in attention restoration (2015). Journal of Environmental Psychology
- The impact of hedonic social media use during work breaks on recovery experiences and return to task performance (2024). Scientific Reports